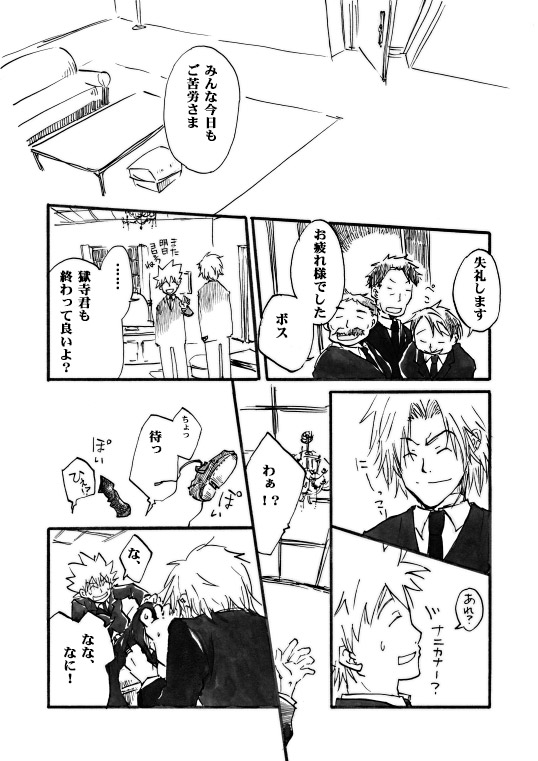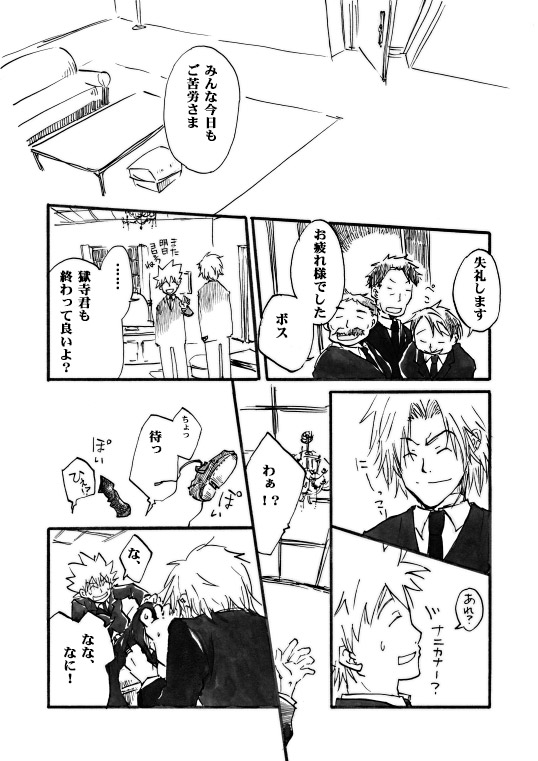|
しれっととんでもない箇所に口づけを捧げた男はそのまま脚にすがって顔を伏せてしまった。
ひと息に体温が二度も三度も上がったが、銀の髪から覗く耳が少しずつ赤みを帯びていくのを見るにつけ、落ち着きを取り戻す。
(そうか、まだ)
気づかれていないのだと思うと、自賛と自省と申し訳なさ、そのうえによくわからない可笑しみすらも内包する分類しがたい心持ちになった。
口惜しげに言葉を搾り出した相手には悪いが、そんなことはとっくの昔、今の立場を公に口にした瞬間から、当たり前におのれの身の内に許していたことだったので。
そう、もうずっと何年も前から守りたいものは両の手からあふれた。たった二本の腕ではてんでかばいきれない。いまやどれだけ自分のものではない『もう二本』に甘えきっているか、家庭教師やら親友に指摘されるまでもない、公然の当然だと思っていたのに。
――肝心の持ち主に自覚がないなんて!
思わず人悪くくつくつともらせば、斜め下から恨めしげな目を向けられた。
(ほら、きみだって)
オレ相手にそんな顔ができるようになったくせに、とますます顔が緩んだ。それでいていまだたかだか靴擦れを隠したことを嘆いたりする! 面映い、というのはきっとこういうときに使うのだろう。
「骸みたいに自分の手足だと思えって?」
彼らの持つ一体感も確かに悪くはないと思うけれど。
「……不本意なたとえですが」
いつもはとんでもなく正確な音を紡ぐくせにくぐもった聞き取りづらい声は、それはそれは珍しいことに拗ねて響いた。
もう少し見栄を張っておきたかった気もするが、どうやら改め時らしい。こっそりと気合を入れて唇を湿らせ、深呼吸をひとつ。
「いやだね」
吐く息でばっさり切り捨てる。
わかりやすく素直に衝撃を受けて、浮いた顔を両の手で捕らえる。拳を作るせいか骨の太いずんぐりとした手指は、白皙の玲瓏にそえると我ながらますます不恰好に見えたけれど。
守りたいものをしっかりと握れるのならそれでいい。
触れた暖かさをきちんと受け取れるならそれでいい。
意図を読み損ねて疑問符と怯えを明滅させる両頬を、手のひらでつまむ。
「でゅー、ひゃい、へ?」
「オレは、オレのじゃない腕が、オレの大事なものを一緒に持ってくれるのが嬉しいよ?」
あんまり甘やかしてくれるから、その分喪失への恐れは根深くて、いっそ自意識を溶かして一緒になって融解してしまえばいい、なんて狂う夜もないわけではないけれど(そんなのは秘密だ誰にだって言えやしない一生の秘密だ)、それでも眠れないままでも目を閉じて、容赦ない朝が来てくれればフタをできる程度のことだ。
いつもの調子でいつものようにお日さまみたいなぴかぴかの声で呼んでもらいさえすれば、とりあえずはどこかへしまってしまえるくらいのことだ。
「そりゃーもう、君とか山本にはすっかり無遠慮だけどね……」
じっとこちらを伺う翡翠から逃れたくなって頬を離し、銀の頭を抱え込む。
タバコの苦みとくたびれた今日一日を想起させる温(ぬく)みは、いつのまにやらすっかり身に馴染んだ安定剤だ。
行きたい場所、目指す方向にきっとついてきてくれるという確信の面映さは、いつでも変わらぬ大切なお守りで。
それと同時に『当たり前のことではない』のを忘れてはいけないのだと、何度もなんども胸に刻む。
「遠慮なんか――」
「遠慮じゃないよ、……えーっと、根源ってヤツだ」
道を指し示すものと、背中を押すもの、引っ張ってくれるもの。
今の自分を形作る根っこ。
ダメツナを肯定する『他者』。『自分』の輪郭を描くための基軸。
「きみはオレじゃなくていいんだ。オレじゃないからいいんだ」
献身は要らない。
助力があれば良い。
感覚的な言葉遊びに過ぎなくても、オレのじゃないオレの右腕であってほしかった。
「……やっぱり」
たっぷり数十秒は溜めた後、「いじわるなのは10代目です」だなんて深々とつかれたため息は、過ごした月日に比例して、オレを喜ばせただけだった。
|