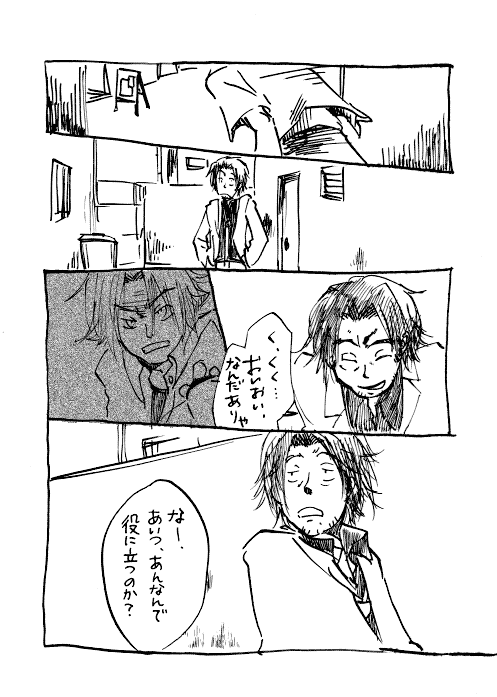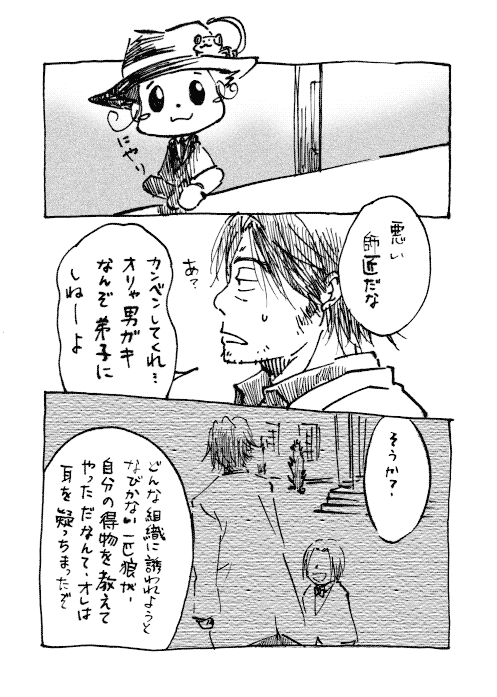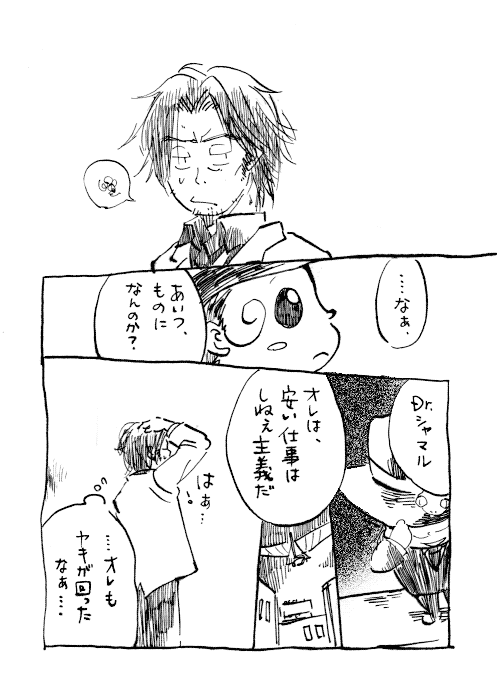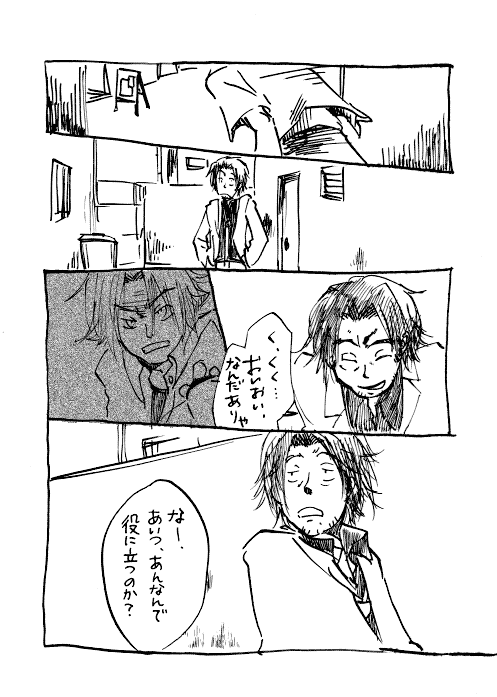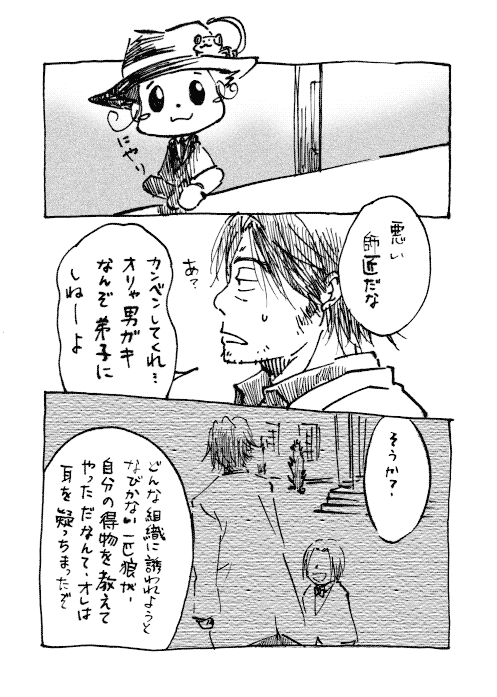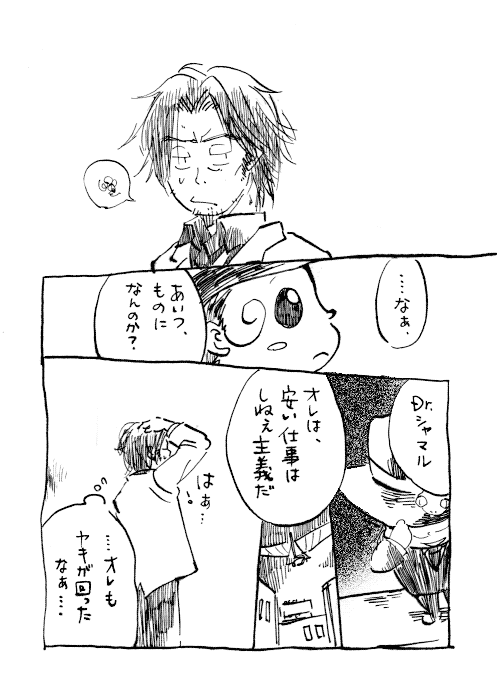|
昨日はほんと散々だった、と綱吉はさわやかな朝に似合わないため息を長々とついた。
治療してもらったとはいえ不治の病だったのだ、いつもよりずいぶん早い時間に倒れるように床に就いたが、それでも今も全身重い。
(……違うかぁ…朝、めんどうなのはいっつもか)
とぼとぼと通学路をたどりながら、理由の違うため息をもう一度。
母なんかはため息をつくと幸せが逃げる! なんて言うが、綱吉に言わせてみれば、つらいことを我慢して体内に留めている方がよっぽど不幸せだと思う。
死なずに済んだのは行幸だったが、代わりに家庭教師と交わした約束が気鬱だ。
(十番以内とか絶対無理!)
赤点を免れるだけでも精一杯なのに、上から数えて……なんて、無謀の極みだ。
そう思うのに、果たせなければ、きっとその日があらためての綱吉の命日になるに違いない。あのカテキョーはやると言ったらやる。絶対だ。
残夏、気温はまだまだ高いのに、ぞくり、と身を震わせた綱吉の視界に、遠目にも目立つ銀色がきらめいた。
古ぼけていつもどことなくうらぶれて見える児童公園の、朝日にさんさんと照らされたブランコに座って、タバコをふかしているらしい。猫背の後ろ姿はしょんぼりと――そんな彼は初めて見た!――丸まっている。
ぱくり、と口を開きかけて、慌てて閉じる。
(声かけてどうすんだよ、オレ!)
学校でだって怖いのに。こんな、まだあまり人のいない公園で対峙するにはおっかない相手だ。
そっと静かにやり過ごそう、と息を潜めて止めていた足を送りかけて、足元の吸殻の量に絶句する。
昨日早く寝たから、疲れてはいるけれど、きちんとした時間に起きた。余裕を持って通学できるくらい。つまり、まだ時刻は早い。それなのにあの量だと、彼はいったいいつからあそこにいたんだろう?
かばんを持つ手を無意味に右から左に変えて。
それでも、ちょっと気合が足らなくて。
「ごくでらくん」
声は時期遅れの蝉に押されてひどく弱々しいものになったけれど、丸い背中がバネ仕掛けのおもちゃみたいに跳ねた。
「ぉおお、おはよー…?」
立ち上がった勢いとは裏腹に、今度は油の足りないロボットみたいなぎこちなさで振り向く。
無言のままじっと見つめられてハッキリ言ってかなり怖い。もう裸足で遁走したいくらいの心持ちだったが、なんとかかんとか勇気を振り絞ってにへらと笑って見せれば、強張っていた面をふっと緩めた。あまり見たことのない種類の顔、綱吉の前では気合を入れて神経を正の方向へも負の方向へもどちらかにめいいっぱい張っている、そういう表情ばかりだったけれど、そうじゃない顔だった。
なんだか初めて遭遇した気がする事態に戸惑っているうちに、長い距離を三歩で詰めて、「おはようございます十代目!!!」と頭を下げたときには、もういつものとおりだった。
「かばん、お持ちしますね!」
「えええ、いや、いい」
よそんなの、と綱吉が言い終わる前にすでにかばんはあちらの手の中。
「お疲れのように見受けられましたので!」
にこにこと笑う姿には先ほどの面影はどこにもない。
けれど、確かに見てしまった違和感は拭い去りがたく残って、綱吉の心をざわめかせる。
(なんだろう、わかんないけど……)
そっと見上げて盗み見た顔は、普段どおりきらきらしく朝日を浴びて力強かったけれど。
「……わかる?」
きっと、さっき見てしまったのは、綱吉にもよく覚えがあるものだ。
「聞いてよ、獄寺くん。昨日なんかひどくてさ!」
そういうときは、路傍の花があったかい色をしているだけで嬉しかったり、涼しい風が頬を撫でるだけでも慰められた気分になるのだ。
だから、たぶん、ダメツナがちょっとくらい馴れ馴れしくしても気には障らないだろう。
「リボーンのヤツ、横暴にもほどがあるよ」
気を紛らわせることくらいできるだろう。
精一杯道化のようにおどけて見せる裏側で(まぁ、頑張らなくても鈍くさいのは標準装備で無問題なのだけれど)、ほんのちょっぴり肩の力を抜いた。
緩めて見せてくれた顔の分だけ、力を抜いた。
|