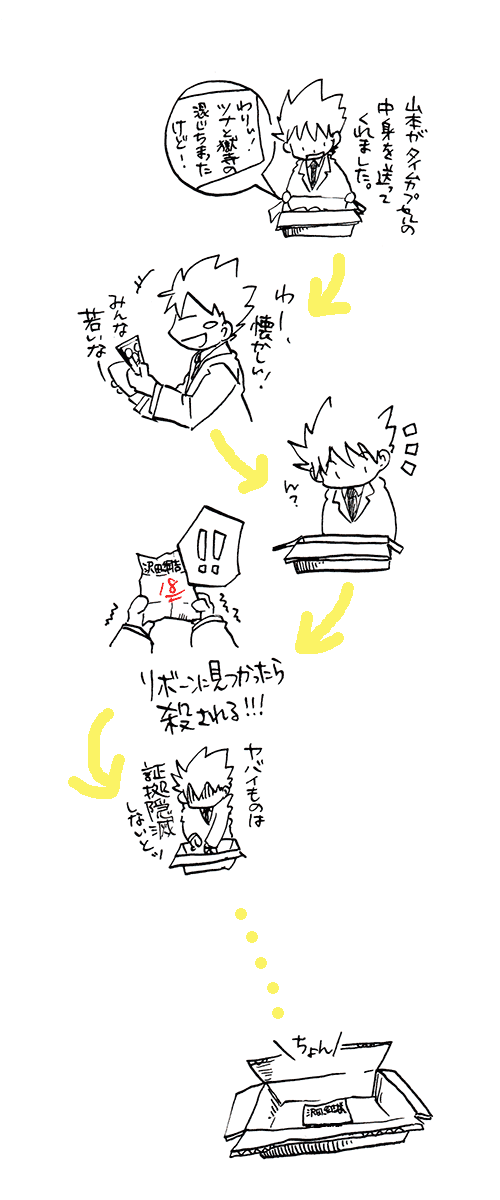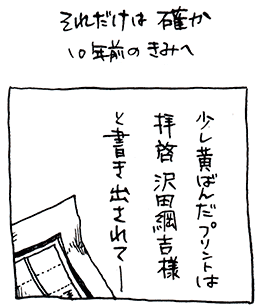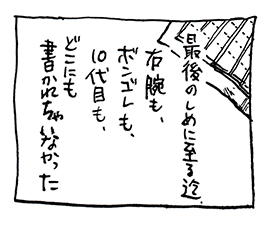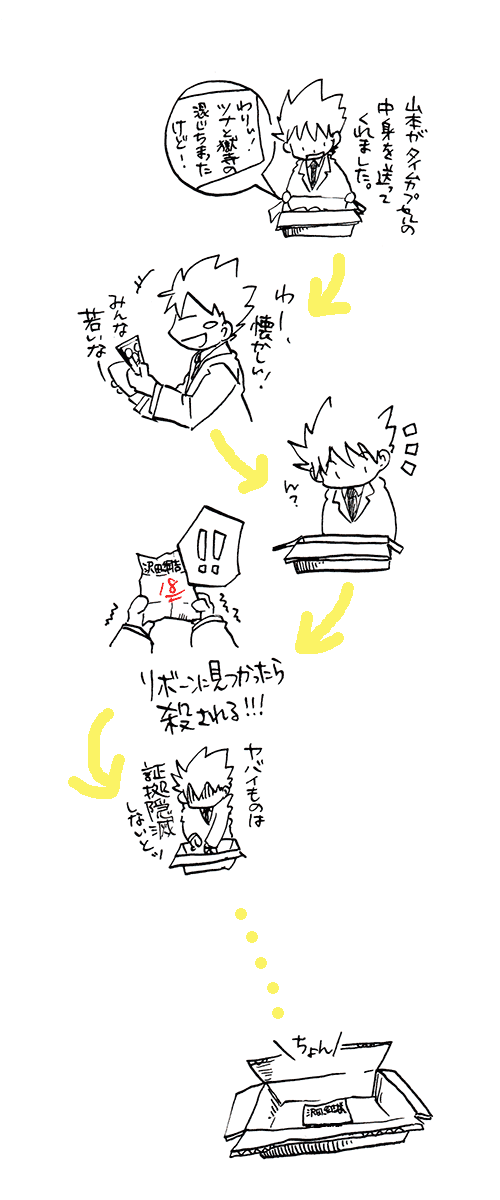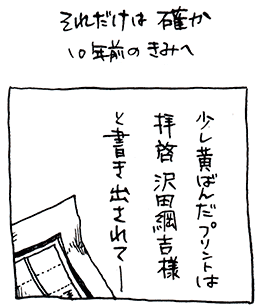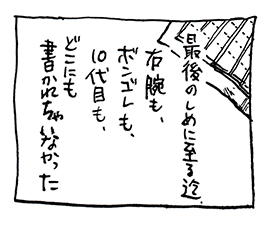|
主の涙がシャツをじっとり濡らすのを獄寺は黙って耐えた。
何を謝られるのかちっともわかりはしなかったが、そんな必要はないのだと、ぎゅっと、胸深くに抱え込む。
書いた言葉は、もちろん、一言一句覚えている。
他愛ない、ガキの浮かれた恋文のようだった。
ひたすらひたすら、主がお元気でいるだろうか、ご立派になられているに違いない、今おれは(当時。十年前のことだ)あなたのおかげで、こんなにも日々心安く、充足し、幸福だと、どれほど言葉を尽くしても足らないことにもどかしさを覚えながら、書き連ねたことを覚えている。
教師の言を取り違えたそれを破棄しなかったのは、いったんは捧げたものを己の都合で取り下げるのに躊躇したのと、十年ののち万が一――どころか十に一くらいは、おそばにはべっていないだろう自分を、タイムカプセル、などという軽薄な学校行事ででも思い出していただけたら、という誘惑に勝てなかった結果だ。
「オレ、十年前にね」
もそもそと顔を埋めたままの言葉はこもって少々聞き取りづらかったが、もちろん聞き逃すはずもない。
「あの手紙を書いた君は」
背中に回された手のひらがぎゅっと背広にしわを作った。
「少なくとも十年後のオレのもんだって」
思ってた、と!
「……でも、あん頃だって、君はちゃんと<オレ>を思ってくれてたんだねぇ…」
お顔を拝見したくても、引き離すなどできはしない。
せめて、つむじに唇を捧げて、ここは拗ねてもいいところだろうか、と獄寺は贅沢な悩みに悩む。
オレはいつだってあなたのものだけれど、十年前の自分にだって、今のあなたを取られるのはお断りです!
と、主張してもいいだろうかと、主の涙の止まるのをじっと待つ。
|